日本新聞協会が主催する第74回新聞大会は11月17日、岩手県盛岡市の市民文化ホールで開かれた。恒例の研究座談会では、東日本大震災の発生から10年の節目の年に、災害報道におけるメディアの役割や、新聞経営の課題について議論した。パネリストのほか、フロアにいる全国紙、地方紙の社長らが相次いで発言。それぞれが自社の取り組みなどを語り、新聞業界の課題や今後の方向性について、情報を共有した。
「報道は災害にどう向き合うのか」
日本新聞協会・丸山昌宏会長(毎日新聞社社長)

報道は災害にどう向き合い、記憶と教訓を次の世代にどう伝えていくべきか。
岩手日報社・東根千万億社長

岩手県も被災地になった東日本大震災は、「1000年に一度」の大災害と言われている。私たちは1000年後の人たちの評価に応えられるような報道を心がけ、活動を続けている。
一人ひとりの尊厳を大切にし、次世代のために大人たちが立ち上がって努力する姿勢を見せることも頭に置いた。大震災直後の被災者名簿の掲載も、その一例だ。
また、人々の立ち上がる姿を報道するだけでなく、私たち新聞社も行動で示さなければならないと考え、県外での号外配布などさまざまな取り組みもしている。
災害報道は「安全最優先」
中国新聞社・岡畠鉄也社長

広島県では広島土砂災害、西日本豪雨、今年8月にも過去に経験のない大雨に見舞われた。「異常気象は毎年起きる」との前提で向き合っている。
私たちは災害報道で痛恨の過去がある。2006年に集中豪雨を取材していた当時20代の記者が行方不明のままだ。彼が残した「安全最優先」という教訓を、今も基本方針に掲げている。徹底しているのは、取材の安全が確保できないうちは、現場に行かない、行かせないことだ。災害報道では「3勤1休」を原則にしている。
デジタルにも力を入れている以上、災害時も初動が大事なのは言うまでもない。災害時などには、放送局に視聴者から多くの映像が
送られてきて、今や災害ニュースには欠かせない素材となった。新聞社に送られてくる動画は少ない。新聞社もデジタル発信を強化していることを、もっと認知してもらうことも必要だ。
災害報道で心がけていることは「地域を守る」こと。中でも救える命を救うことだ。つまり「避難文化」の醸成が重要だ。避難する意識を高めるためには、日常的な問題提起をする。そのために今年9月から防災に関する特集ページ「防災 命を守るために」を始めた。今後は教育現場などとも連携したい。
朝日新聞社・中村史郎社長

被災地にしっかりと向き合い、長期的、継続的、多角的に報道していくことだ。特に全国メディアとしては、さまざまな災害事例をできるだけ横につなげたり、災害とは直接関係ないようなテーマを結びつけたりして、読者の関心を継続的につなぐ試みを続けている。
紙面での特集や連載だけでなく、シンポジウムやフォーラム、コンサートを大学や企業、市民と一緒に展開し、この10年で防災を考える試みも集中的に取り組んできた。
経験と教訓の伝承も役割
丸山 それではフロアからご発言いただきたい。まず、東日本大震災の被災地の地元社から。
河北新報社・一力雅彦社長

被災地の新聞社として、震災の風化を防ぎ、経験と教訓をしっかりと伝承していくことも大きな役割だ。「むすび塾」「次世代塾」のほか、今年度は中学生を対象にした「かほく防災記者研修」も始めた。
社内では震災を知らない社員が一定数を占め、若い記者からは被災者にどう向き合えばいいのか分からないとの声も聞かれる。震災を取材した先輩の経験やノウハウを、社内外から学ぶ機会を増やすことも課題だ。毎月11日付朝刊で続けている防災特集面について、来年は取材・執筆をすべて入社10年までの若手記者に任せてみようと考えている。
また、大きな自然災害時には人命と安全を最優先し、新聞輸送・配達業務を中止するなどの新たなガイドラインも策定した。新聞輸送トラックの全車にGPS付きのスマートフォンを配置するなど、安全管理の精度向上にも務めている。デジタル分野も強化している。こういったことを周知するため、台風シーズン前に読者へチラシを配布したりもしている。
福島民報社・芳見弘一社長

福島県は震災と原発事故の複合災害が、現在進行形で進んでいる。被災地の地元社として、記者らの放射線教育の充実もしなければならない。他の地域で起こ
った自然災害時にも、記者を派遣するなどしながら教育している。地元ラジオ社と一緒に実施している「夜の避難訓練」も、大事な取り組みだと考えている。
現在の小中学生に震災時の記憶はほとんどない。震災や原発事故を自分ごとと捉え、命を守ってほしいとの思いから昨年と今年、絵本『きぼうのとり』を発行した。本紙でも紙面化したり、県内外の学校にも寄贈している。音声配信による読み聞かせもあり、ドイツでも行われたという。全国、世界に届く本という媒体も、地方紙にとって大きな武器になることが分かった。
11月10日には東京都内で、東京新聞と震災10年のイベントを開催した。やはり首都圏で発信は大きな力になり、地方紙同士がつながることで力が生まれると改めて実感している。
福島民友新聞社・中川俊哉社長

私たちも若い人への伝承が重要との思いから、絵本「ぼくのうまれたところ、ふくしま」を発刊している。伝承施設とも連携しており、今後もさまざまな形でコラボして若い世代への記憶と教訓の伝承を図っていく。
原発事故の発生以降、特集ページなどで伝え続けている。地方紙はマンパワーに限界があり、記者が心身ともに疲労しないよう継続的なケアも必要になる。震災後、若い記者が社を去ったことを振り返り、教訓としている。
そのうえで、原発事故と廃炉の取材は科学分野の専門知識が必要で、対応できる人材を継続して育てる必要がある。被災者への報道についても、彼らが実名で答えてくれるような取材力、説得力、人間関係づくりが報道機関共通の課題だと考えている。
また、福島県に関する誤情報は今も発信されている。私たちは国内外で誤った情報が伝わった時点で、何が違うか、何が問題かを訴えてきた。事実を報じていく報道機関として見過ごしてはならないし、地元紙が動かないと小さな誤りも蓄積されてしまうからだ。
新聞社が被災地と未災地をつなぐ
神戸新聞社・高梨柳太郎社長

阪神・淡路大震災から20年目に六つの提言を紙面で発表した。考え方のベースにあるのは「攻めの防災」で、その一つが「防災省」の創設だ。国内最大級の防災イベント「防災推進国民大会」(ぼうさいこくたい)が来秋、兵庫県で開かれるので、その場でも今一度アピールしていきたい。
次世代の引き継ぎでは、大学生と組織をつくり「ぼうさいマスター」の認定も続けている。これまで1500人ほどが生まれている。
コロナ禍でも都市部のもろさとともに、地域やローカルが見直されている。地域に軸足を置くメディアとして、しっかりと地域の豊かさや可能性を掘り起こす取り組みを続けていきたい。
静岡新聞社・大須賀紳晃社長

今年夏、静岡県熱海市で土砂災害が起こった。今後も大きな自然災害が想定される。私たちは編集だけでなく営業、事業部門も含めて、幅広い新聞社の資源を生かして取り組みを続けていく。
防災情報をさらに分かりやすい言葉で伝える努力、研究者と読者とをつなぐ記者の育成が、これまで以上に重要になってくるだろう。そして、伝えた情報をどう生かしてもらえたかまで、責任を持って考えていかなければならない。しっかり伝わり、しっかり使ってもらえる防災情報の発信に力を入れ、コミュニティづくりの支援に取り組んでいく。
高知新聞社・中平雅彦社長

南海トラフ地震では、高知県も大きな被害が予想されている。河北新報の「むすび塾」を通して、紙面展開だけでなく、住民と一緒に考え行動することの大切さを学んだ。毎月1回、特集の地震新聞で防災情報を発信し、2016年に防災プロジェクト「いのぐ」を始めた。若い世代の被災地への視察などを続けている。
まだ災害が起きていない「未災地」で防災の実効性を高めるためには、リアリティが重要だ。被災地と未災地をつなぐ役割を果たし、南海トラフ地震に備えたい。
紙の力をどう使っていくか
丸山 フロアからの報告を受けて、パネリストの皆さんにお聞きしたい。
岡畠 地元紙として最も力を入れなければならないのは、残念ながら犠牲になった方々の生きた証しを読者と共有することだ。かけがえのない一人ひとりの命の尊さを地域で共有する。それが災害の風化にもつながる。土砂災害の報道では、70人超の犠牲者の顔写真と人となり、歩みを掲載した。
災害報道において、自治体が犠牲者の身元を明らかにしないケースが増えている。熱海の土砂災害でも、行方不明者の公表が捜索活動の迅速化につながったと言われている。もちろんメディアスクラムをしないことなどを前提に、公表の有効性を訴え続けていかなければならない。
中村 各社の発言を聞き、共通する悩みや課題を抱えていることが改めて分かった。
災害時は、どうしてもSNSの情報が拡散しやすい。その中にはフェイクニュース、デマも広がることは皆さん経験しているだろう。その時に、新聞社が発信する情報は確かだと、多くの市民、読者、ユーザーに知ってもらう努力を、業界全体で続けることが重要だ。
誤情報が発信される時こそ、私たちが持っている取材力などを発揮して「この情報はデマだ」とか、「この情報は確認されていません」などと発信していくことも必要だ。高齢者を含め、幅広い人たちい情報を届けるために、紙の力をどう使っていくかも考え、実行している。
東根 東日本大震災の時、災害報道で過労を防ぐ難しさを経験した。アメリカ軍からヒントを得て、辛いときに「がんばれ」というばかりではなく、記者には現場を離れて気持ちをリフレッシュさせることもした。人材のやりくりが大切になるので、次なる災害に向けて現場を指揮するべき管理職、役員らをどう鍛えていくかを考えている。
これまで私たちの先輩方も、大きな災害などを経験し、乗り越えてきた。今後も大災害は起きてほしくはないが、乗り越えて進化する面もあることを、頭に入れていきたい。
「これからの新聞社経営を探る」
丸山 次に今後の新聞社経営について、まず販売、広告関係の話を聞いていきたい。
中村 紙の新聞については、若者の購読対策、固定費削減など各社の課題は共通している。その解決方法の一つとして印刷や配送、配達、編集システムなどサプライチェーンの効率化などで、各社が協力を強める流れが加速するだろう。当社もそれらに力を入れている。
一方、今後に欠かせないのはデジタル分野だ。しかし、そのビジネスモデルの確立は試行錯誤の段階だろう。業界全体では「ニュースは無料」「こたつ記事」「フェイクニュース」などに対抗する必要がある。
私たちも「朝日新聞デジタル」が10周年を迎え、新しい価格帯を設けたり、記者を交えたイベントなどで付加価値を高めている。
東根 私たちは「元祖・戸別配達網」を持っている。それを強化すれば魅力が増す。
発行本社も販売現場を知るために、管理職の販売店研修を始めた。元旦号をセットし配達する12月31日から元旦の現場を見学するため、「大みそかの販売店見学・研修バス」を出そうかという構想もある。「豪雪対策研究会」も設け、大雪の時こそ配達員の安全を確保しながら新聞を各戸に届ける方策を検討している。
広告関係では、岩手日報広華会を通じて、社会貢献などに取り組む。総勢500社を超える会員の声を生かして、岩手の未来を考えていきたい。政策提言するシンクタンク的な存在に発展させられるだろう。
岡畠 中国新聞社のデジタルの着手は比較的早かったが、10年足踏み状態が続いた。本格的な参入は3年前の「カープ公式アプリ カーチカチ!」のリリース。それ以降、ヤフーやグーグルへの記事配信、SNS展開、音声サービス「Voicy」などあらゆるツールを駆使している。
そのかいもあって、一昨年のメディア収入が初めて1億円の大台を突破した。昨年度は2億円、今年度も順調に倍々ゲームが続いている。
また、11月から若者を対象にしたウェブ媒体「中国新聞U35」を始めた。プラットフォームを運営企業の「note」とタイアップしている。
デジタルを進化させるのに欠かせないのが「人材」だ。徹底的に外部の知見を活用している。IT系スタートアップ企業と連携し、新規事業の実証実験も行っている。
一方、コロナ禍で改めて販売収入、戸別配達網の維持が私たちにとっての生命線であることを痛感した。
販売所支援のため、旬の逸品や話題の一品を紹介する中国新聞販売所宅配サービス「おとどけ Ippin帖(イッピンチョウ)」を今春から始めた。売り上げは約6000万円、粗利が1500万円、そのうち販売所の取り分を65%に設定している。また、広島県呉市でも10店の販売所が共同で、オンラインショップを開店する事例も出てきている。
配達力生かし収入源を複線化
丸山 それではフロアからご発言いただきたい。
読売新聞東京本社・山口寿一社長

販売店の配達力を生かし、収入源の複線化をはかっている。具体的には、マクドナルドのデリバリーやYCお届け便などで、それぞれ今後も拡大する見通しだ。
折込の振興では、販売店自らが営業する小口の折込も直近1年間で4000件以上にのぼっており、さらに強化していきたい。また、総合広告会社やネット広告会社など5社による「リテールアド・コンソーシアム」を設立し、折り込みとネットを組み合わせた最適な広告手法を研究・開発している。
広告部門では、デジタル系企業とのコンソーシアム「YOMIURI BRAND STUDIO(ヨミウリ・ブランド・スタジオ)」や、新聞広告を起点にしたSNSでの拡散を捉える「よみバズ」も進めている。
北海道新聞社・広瀬兼三会長

地域を元気づけるための施策を進めている。例えば、コロナ禍で部活や学校行事が中止になった高校3年生の思い出づくりを応援しようと、卒業式シーズンに照準を当てて音楽、映像、新聞などを組み合わせた「未来のきみに贈る歌(#ミラ歌)プロジェクト」を展開し、大きな反響を呼んだ。北海道教育委員会の事業の一環として、私たちが函館出身のロックバンド「GLAY」や道内出身の漫画家、著名人の協力を得て企画。道内外の50以上の企業・団体から協力、協賛も得た。
下野新聞社・岸本卓也社長
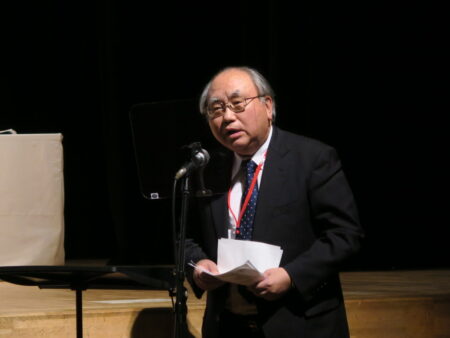
新聞広告を軸としながら、地域の課題解決に向けた事業に取り組んでいる。18年に実施した交通啓発キャンペーン「TEAM STOP TOCHIGI」に手応えを感じ、認知症に対する不安や恐怖、偏見を取り除くことなどを目的とした「認知症カフェプロジェクト」をスタートさせた。営業局がNPO、ボランティア、関係団体らと話し合いを重ね、協賛してほしい県内クライアントにも、地元が一丸となって取り組む課題だと、丁寧かつ地道に説明。多メディアで展開している。
「地域応援会社」として展開
丸山 ここからは新たなビジネス展開についての取り組みを聞いていきたい。
東根 新たなビジネスも模索しているが、優先しているのは既存のものを活用することだ。例えば、最先端の高速輪転機の活用に全力を挙げたい。出版部門の可能性も追求してみたい。作った本をどう売るか、販売力を強化する。持てる設備、得意な分野をさらに活用すべく、徹底的に努力する。
岡畠 今年8月、東京や地元企業で構成するコンソーシアムに参画し、広島市が進めるPFI事業に名乗りをあげた。旧市民球場跡地を再整備し、新たなにぎわいの場をつくる事業だ。スポーツや祭典など多様なイベントが展開できるスペースなどが作られる。私たちはイベントの企画・運営、宣伝・広報を担う。また、昨年にも地元の銀行、鉄道会社と地域商社を立ち上げ、平和記念公園内にあるレストハウスの指定管理を受託している。
新聞社には長年培ってきた信用力や発信力などがある。それが地域の価値の向上につながるという思いから、公的事業に参画している。新聞社として「地域応援会社」の展開にも磨きをかけたい。
中村 13年に新事業の社内公募制度を始めた。自分史事業やクラウドファンディングなどいくつかが事業化され、社員のモチベーション向上や意識改革につながっている。
同時に今持っているアセット、ブランド力も生かす必要がある。朝日新聞社、グループ企業が持つ力を有効活用しようと呼びかけている。その中で、オンライン共通の「朝日ID」を重要視している。
丸山 またフロアから発言していただきたい。
中日新聞社・大島宇一郎社長

来年22年秋に、愛知県長久手市の愛・地球博記念公園に「ジブリパーク」が誕生する。開業後の管理や運営は、中日新聞社とスタジオジブリが共同設立した㈱ジブリパークが務め、私が社長を務める。愛知県はものづくり産業ばかりが目立ち、観光が弱い。また、名古屋市栄に改築している「中日ビル」も工事が本格化。筋向かいにあるビルの建設計画もあり、出資することになった。地域活性化のため、社内の壁を越えた形で、私たちができることを推進していきたい。
新潟日報社・小田敏三社長

私たちは今年4月、全国で古民家再生事業などを手がけるNOTE(兵庫県)と共同出資し、まちづくり会社「Essa(エッサ)」を設立した。佐渡金銀山がある佐渡市相川地区のプロジェクトを皮切りに、事業をスタートした。これは昨年あった神戸市での新聞大会をきっかけに、神戸新聞社にご紹介いただいた。佐渡の歴史的資源を活用し、観光振興や活性化事業に取り組む。地域に入り込み、地元と一緒になってまちづくりを進めている。ひとつの成功事例になればと期待している。
山陰中央新報社・松尾倫男社長

コロナ禍で地元の事業者を支援するため、島根県がプレミアム付き飲食券と宿泊券を発行した。チケットの印刷、広報、金融機関との連携、決済システムづくり、販売店を通した配達、集金など、社内のリソースを使って取り組んでいる。県内に200の販売店があるが、20万円から100万円を超える配達手数料の収入があり、経営の一助になっている。県内販売店から全戸配布できる態勢も構築することができ、地域住民からも大変喜ばれている。戸別配達網の強化にもつながっている。
愛媛新聞社・土居英雄社長

今年の春、小中学生向けのICT教育専用サイト「愛媛新聞forスタディ」(eスタ)を始めた。社内公募制度でアイデアを募集した。提案者らがスピーディーに仕事を進め、販売部など各部署も積極的に協力することで、県内全ての教育委員会を訪れ、直接説明することに成功した。現在、県内20市町のうち19市町、利用可能な生徒数は97%にあたる9万8000人にのぼる。現場のニーズをタイムリーに捉えた結果。新規事業はアイデア、意欲、関係者とのコミュニケーション、スピード感が重要だ。
西日本新聞社・柴田俊哉社長

17年に新規事業の開発、M&Aや異業種との業務提携などを担う「ビジネス開発局」を発足させた。私たちの「地域ジャーナリズム」を守ることが、最大の目的だ。一つは不動産、二つ目はM&A、三つ目は新規事業にそれぞれ取り組んでいる。正直に言うと、全てが計画通りにうまく進んでいるわけではない。しかし、チャレンジできるのは今しかないと考えている。社内的に最大の課題は「人材」だ。外部の力を借りながら事業を推進したり、社員を育成していきたい。
熊本日日新聞社・河村邦比児社長

新聞社の大きな強みは「つなぐ」という機能。人、地域、自治体、企業などをつなぐ役割の中で、新たなビジネスチャンスを見出しているところだ。その一例がeスポーツ。推進派と心配派を私たちがつなぎ、協会を発足させた。もう一例が企業によるふるさと納税がある。自治体と企業をマッチングする役割を担っている。地域としっかりと寄り添う伴走型ビジネスを進めているが、このベースにあるのが2年前に設けたコワーキングスペース。新たなビジネスの芽を生んでいる。
南日本新聞社・佐潟隆一社長

新聞活用学習支援サイト「すくーる373(みなみ)る」を始めた。子どもたちに新聞を手軽に読んでもらう、地元の記事を教材に使ってもらう、離島・へき地の教育と情報格差の是正などがコンセプト。サイトは自社開発した。鹿児島や世界の今を伝える新聞として、授業・学活に役立つ5つのメニュー、投稿機能や検索機能を搭載している。使用料は児童・生徒1人につき年間900円に設定している。初年度の今年は7市町村で使っていただいている。
読者に寄り添った報道に磨きかける
丸山 最後に、パネリストに一言ずついただきたい。
岡畠 私たちは来年、創刊130周年を迎える。先人が培ってきた地域との信頼関係があってこそだ。しかし、地域は今、私たちが思うほど新聞社に信頼を寄せているのだろうか。地域のジャーナリズムを守るうえで、もし地域の信頼が崩れているとしたら、新聞経営そのものが成り立たない。それを取り戻すには、新聞の原点に戻ることしかない。読者に寄り添った報道、情報発信に磨きをかけることに尽きる。
河井克行元文部大臣の大規模買収事件では、初報は『週刊文春』だった。内部告発者は私たちではなく、週刊誌を選んだ。政治スキャンダルは「文春砲」という流れを深刻に受け止めなければならないのではないか。足元を見つめ直すことも、これからの新聞経営を確立するためにも必要なことではないか。
中村 新聞大会はここ数年、新聞社の経営基盤強化や新たな事業展開が大きなテーマとなっている。年1回の大会だけでなく、もっと日常的に意見交換、共有できればいい。
また、今大会で女性が発言する機会が一度もなかったことが気になった。紙面で多様性とか言いつつ、こういう場で男性ばかりが発言している状況はどうなのだろうか。
東根 最も重要なのは「人材」だ。新聞社としての知的レベルを高めなければならない。例えば、科学分野をみても非常にハイレベルで、細分化されている。それらを分かりやすく伝えるためには、新聞社として知力を高めないといけない。そのために、人材への投資は最優先で取り組んでいきたい。
丸山 多くの情報を共有できて有意義な討議となった。ありがとうございました。
